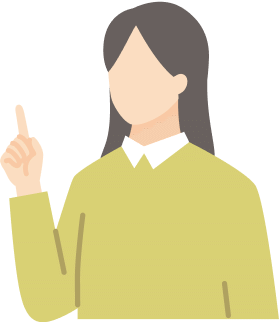保育や介護の現場では、毎日が人と人との関わりの連続です。子どもや高齢者と過ごす中で「ヒヤッとした」「ハッとした」瞬間に出会うこともあるのではないでしょうか。
これらは「ヒヤリ・ハット」と呼ばれます。事故や大きなトラブルには至らなかったけれど、「もし状況が少し違っていたら危なかったかもしれない」という出来事です。一見すると「大丈夫だったから良かった」と思ってしまいがちですが、そのままにしておくと同じことが繰り返され、大きな事故につながる可能性もあります。
だからこそ、日常の中で起きる小さな「ヒヤリ・ハット」を見逃さず、記録・共有・改善につなげていくことが、安心・安全な現場づくりのカギになるのです。
保育・介護の安全管理|ヒヤリ・ハット事例から学ぶ予防と仕組みづくり
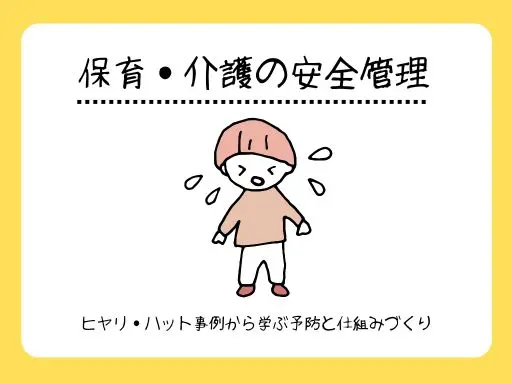
~小さな気づきが大きな安心につながる~

1. 保育現場でよくあるヒヤリ・ハット
子どもは元気いっぱいで、行動の見通しが難しいこともしばしば。小さな事故の芽は、こんなときに顔を出します。
たとえば…
・遊具やブロックで遊んでいて、友だち同士がぶつかりそうになった
・食事中に咳き込み、誤嚥しかけた
・お散歩中に列から外れ、車道に近づいてしまった
こうした場面は「大丈夫だったから」で終わらせず、「なぜ起きたのか」「どうすれば防げるか」を考えることが大切です。
たとえば遊具の使い方を再確認したり、お散歩の際の並び方を工夫したりといった小さな改善で、安心感がぐっと増していきます。
2. 介護現場でよくあるヒヤリ・ハット
介護の現場では、利用者さんの体調や身体機能の変化によって、思わぬきっかけで危うい場面が生まれることがあります。
よくある事例としては…
・トイレへの移動の際、立ち上がった瞬間にふらついて転倒しそうになった
・食事のときに口に食べ物をため込み、誤嚥しかけた
・車いすのブレーキがしっかりかかっておらず、思わぬ方向に動いてしまった
こうした出来事も、現場の工夫次第で未然に防ぐことが可能です。
たとえば移動の際は声をかけながら支える、食事中はひと口ごとの嚥下を確認する、車いすの点検をこまめに行うなど、小さな習慣が安全につながります。
3. ヒヤリ・ハットを減らすための工夫
大切なのは、起きてしまったことをそのままにせず、どう受け止めて次につなげるかという姿勢です。たとえば「ちょっと危なかったね」で終わらせず、その出来事を簡単にでも記録に残しておくと、同じことを繰り返さないための手がかりになります。
さらに、その経験を一人で抱え込まずにスタッフ全体で共有することも重要です。仲間と情報を共有することで、自分では気づかなかった視点や改善方法が見えてきます。そして定期的に事例を振り返りながら「なぜ起きたのか」「どうすれば防げるか」を考える習慣を持つと、安全意識が自然と高まっていきます。
たとえば、月に一度「ヒヤリ・ハットを振り返る時間」を設けるだけでも、現場全体で意識をそろえることができ、安心につながります。
4. ヒヤリ・ハットを前向きに活かす
ヒヤリ・ハットは「失敗」ではなく「学びの種」です。
一度の気づきを「次は同じことを起こさない仕組みづくり」に変えることができれば、現場全体の安全性は格段に高まります。
例えば、保育園では遊具の配置を変えたり散歩時の声かけを増やしたり、介護施設ではスリッパを滑りにくい靴に変えたり廊下に手すりを増やしたりといった小さな工夫が、大きな事故防止につながります。
まとめ

保育・介護の現場でのヒヤリ・ハットは、誰にでも起こり得るものです。大切なのは「大丈夫だったから」と流してしまうのではなく、「どうすれば防げるか」と考え、チームで共有すること。
日々の小さな気づきを大事にすることで、子どもや利用者の方にとっても、そして働くスタッフにとっても安心できる職場が作られていきます。
YUKUSAでは、安心して働ける環境づくりを大切にしている園や施設をご紹介しています。安全面やサポート体制を重視した転職・就業を考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![【児童発達支援・放課後デイ】[パート]春日部市\保育園併設の療育施設/週3日~相談可!](/upload/JobInfo/images/img_6547_0bfff0cf-3f43-4641-b109-37c3b6d33814.webp)
![【保育士】[パート]志木市♪週2日~OK!1日6時間以上◎小規模園での保育業務☆](/upload/JobInfo/images/img_2938_418905e1-1e98-4926-b47e-c43c89c3990d.webp)
![【児童発達支援・放課後デイ】[正社員]春日部市\保育園併設の療育施設/昇給・賞与◎サポートあり!](/upload/JobInfo/images/img_6415_95d5d7a0-ccbe-46a8-9e13-5c19d6dde78e.webp)